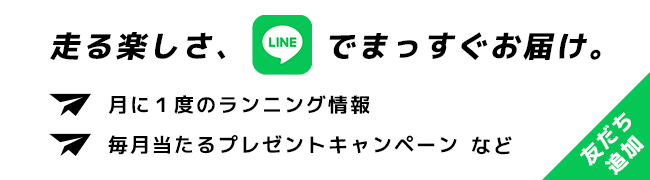「走ること」の新時代へ──多様化するランニングと『RUN.MEDIA』が描く未来

コロナ以降、ランニングの楽しみ方が多彩となり、様々なランナーが生まれました。しかし、多様化するランナーに対して、情報を発信するメディアは枯渇しています。そこで誕生したのが、ニュースレター型 Webマガジン 『RUN.MEDIA』。
今回は『RUN.MEDIA』にスタッフとして参加する「Tarzan」元編集長の大田原透さん、「ランニング・タレント」と数々の大会に参加している中村優さん、フリーライターとして多くのランニングメディアで活躍する神津文人さんの3人に、最近のランニング事情や『RUN.MEDIA』について話を聞きました。

『RUN.MEDIA』は、記録だけに縛られない“走る楽しさ”を届けるメディアです
3人に共通しているのは、記録を目指してストイックにランニングをしているわけではないことですかね。僕自身はランニングブームの立ち上がりから30年近く、業界のいいところ、悪いところも見てきました。そんななかで、ランニングをすることでみんなに元気になってもらいたいと考えています。

本当にその通りで、私自身は、ベストを目指して速く走ることは追い求めてないんです。今まで走ることに縁がなかった人とか、マラソン興味なかった人に、マラソンって楽しい。こうやって走れば楽しいって思ってもらいたいし、走るのが苦手だった人がちょっと走ることを好きになってもらいたいなと思っています。

僕は仕事でランニングやシューズの試走会に呼ばれることが多くて、呼ばれたからにはしっかり走りたい。そのために日々ランニングをするという、言ってみれば「職業ランナー」(笑)。でも、そのお陰で健康を維持できてますね。

『RUN.MEDIA』は、我々のような「普通のランナー」のための、タイム向上のための情報というよりも、「面白くて知識になる」コンテンツを取り上げていきたいと思っています。ちなみに、僕はランシューズのレビューを担当。実際に試走してみて、どんなランナーに合っているかなど、細かくチェックしていきます。

私は、新作発表会やイベントのレポートを担当する予定です。

僕は、ブランドヒステリーやシューズの開発ヒストリー記事など、じっくり読んでもらえるような記事を担当することになります。

そのほかにも、全国のランニングイベントの情報を随時更新したり、ランニング系インフルエンサーと連携し、ポッドキャストによる音声コンテンツの展開も準備中です。

「一度は走りたい」願望と東京マラソンが火をつけた、ランニングブーム20年の軌跡
この20年近くランニング・マラソンブームは続いていますね。その理由のひとつとして「一度はフルマラソンを走りたい」という願望があったと思うんです。それこそ「生きている間に一度は富士山に登ってみたい」のと同じ感覚で。それに、走ってる人はかっこよく見える時代があったんですよね。こういった潜在的な願望や、健康・フィットネスへの意識の高まりもあったところに「東京マラソン」が誕生した。


「東京マラソン」以降、ブームはさらに加熱しましたね。マラソン大会も行政主導のものから民間の大会までかなりありました。次々と大会が誕生したけれど、それでも当時は人気のマラソンイベントはどこも抽選でしたね。ランニングにしても、ランナーの聖地である皇居を走るためだけに地方からランナーが団体で来たこともありました。

そんなブームが加熱しすぎたところにコロナ禍がきてリセットされた。

コロナによって、マラソン大会自体はかなり淘汰された印象があります。コロナ前は行政主導の町おこしイベント的な大会が多くありましたが、そういう大会は復活していないものもありますね。参加人数もコロナ明け直後は苦戦してましたが、徐々に戻ってきた感じがあります。

記録より楽しさ! リレーマラソンやトレランにみる大会の多様化
マラソン大会の参加者も運営もコロナ前後で少しフェイズが変わった気がします。運営者たちががんばって新しい活動をし始めてくれている感じはしますね。運営人数の割にホスピタリティが高いし、値段も良心的、開催場所もアクセスのいい場所でやってくれたり。こういうイベントだと走る気分になるし、みんなを誘って『走り出そうぜ』という気持ちを作ってくれるのは、ひとりのランナーとしてはうれしいですね。

以前のマラソン大会は、いかに記録を狙うか、という雰囲気だったんですが、最近は変わってきてますよね。“日常的に走っているランナー以外”も楽しめる大会が増えている。

象徴的なのは 「リレーマラソン」。コロナ禍以後はかなり増えていますね。ちなみに「リレーマラソン」などを主宰するイベント会社「BOOST」が手がける大会は“走る運動会”のようなノリで、仲間とワイワイ参加する雰囲気があって。DJが入ってたり、ヒット曲が流れていたり、演出面もすごくポップでカジュアルなんですよ。

私もBOOSTの大会に何度か出ましたけど、他の大会と出場者の層がちょっと違う気がします。普段そんなに頑張って走っていないけど、友達や会社の仲間とノリで参加する方が多かったイメージです。


ガチ勢じゃなくても堂々と走れる場所があるのはいいことですよね。コロナ以降、外で体を動かすことに対してポジティブな意識が高まったぶん、「大会に出る=記録を目指す」じゃなくて、「楽しみに行く」という人が増えた気がします。

去年、湘南国際マラソンの「ファンラン 10km」に出たんですけど、めちゃくちゃ楽しかったんです。スタート地点にカフェがあって、ギリギリまでお店にいてスタートへ。友達5人でワイワイ走って、途中でマイカップにドリンク入れたりして、気づいたらゴール。「もう終わっちゃった!」って感じで、フルマラソンと違って緊張感ゼロのゆるさが逆に最高だったんです」

「表参道WOMEN’S RUN」みたいなイメージかな? 確かに楽しそうですよね。

僕もローカルの大会の10kmが好きで走っています。ただ、フルマラソンが部門にある大会だとエントリーの数はフルマラソンがいちばん多い。もう少し、ハーフや10kmといった種目に参加する人が増えてもいい気がしますね。

「走る楽しみ」の多様化−−トレランブームとマラソンの新しいかたち
最近、ちょっとまたトレイルランブームがきてる気がするんですよ。登山じゃなくてトレランを選ぶ人が増えていて、普段走らない人でも『やってみたい』という雰囲気がある。私自身もトレランを再開して大会出たら、若い子が多くてびっくりしました。『白馬国際クラッシック』とか『KOBE TRAIL』だと、音楽がガンガン流れてたり、参加者のファッションもオシャレで。マラソン大会とは明らかに違う空気感があって、すごく楽しかったです。

確かにSNSに上がっている『KOBE TRAIL』の写真を見ると若い人が多いですし、楽しそうでした。あと、ここまでカジュアルではないですが、国内の主要ハーフマラソン6大会が連携した「ジャパンプレミアハーフシリーズ」の創設を発表されましたね。2年間で6大会制覇した人には証明書や記念特典が用意されるそうです。


ワンマイルレースも増えてきたし、フルマラソン以外の選択肢が増えるといいですよね。

やはり、フルマラソンがランニングの入口というのはハードルが高すぎますよね。マラソン大会に出場して記録を出したいという楽しみ方はあるけど、準備は必要だし、自分を追い込むのも大変。

確かに。普段から走っていなくても。ちょっとした旅行気分で参加できる大会があったらいいと思う。

たとえば、いろんな地方大会に参加して、10kmやハーフを友達と一緒に走ったあとに、温泉に入って美味しいもの食べて帰るというスタイルがもっと増えたらおもしろい。今まで「走りたいけど、自分には無理かな」という人たちもイベントとして参加できるし、ランニングの楽しみ方が増えていけばいいと思いますね。もちろん『RUN.MEDIA』でもそういう提案をどんどんしていきたいと思います。


ランニングの楽しみ方はもっと自由でいいと思います。『RUN.MEDIA』は、多様なランナーの声をすくい上げ、共有する場として生まれました。走り方は人それぞれでいい——そんな新しい価値観が広がる今、誰もが気軽に走り出せるきっかけを、このメディアが届けていければと願っています。

大田原透/編集者。フィットネスライフタイルを提唱する「Tarzan」元編集長。1968年生まれ、身長175㎝、体重68㎏。フルマラソンのベストタイムは3時間36分台という典型的な市民ランナーにして、ウルトラマラソン、トレイルランニング、トレッキング、ロードバイクなど長時間&長距離スポーツをこよなく愛す、走って&試して&書く業界猛者のひとり。『RUN.MEDIA』では、基本的にはランニングシューズのレビューを担当。

中村優/ミスマガジン2005でデビュー。2008年ホノルルマラソンで初フルマラソンデビュー。4時間49分54秒で完走。ランニングが趣味に。NHK BS-1「ラン×スマ」でスマイルランナーとして数々の大会に出場。スポーツ系メディアへ出演や、大会のゲストランナーなどランニングタレントとして活動中。笑顔で楽しく走る!無理をしない!がモットー。『RUN.MEDIA』では新作発表会やイベントのレポートを担当する予定。

神津文人/2013年にフリーライターとなって以来、健康とフィットネス、シューズのテクノロジーを中心に「Tarzan」「GIZMODO」「FashionTechNews」「Runners Pulse」などで執筆。『RUN.MEDIA』では、ブランドヒストリーやシューズの開発ヒストリー記事を担当。